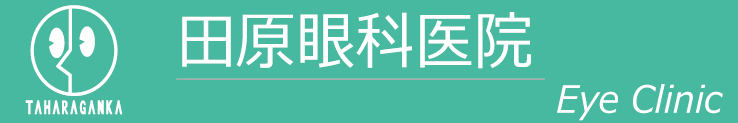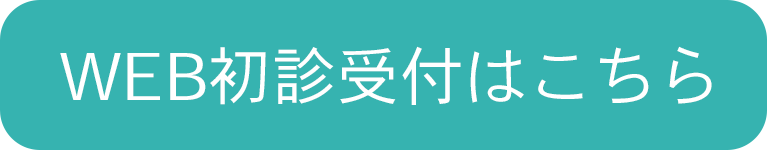眼の病気について
屈折異常(近視・遠視・乱視・老視)
目に入った光(映像)は通常、角膜と水晶体で屈折することで網膜の上に焦点を結びます。屈折異常があると上手に網膜の上に像が結ばなくなり、ぼやけたりかすんで見えたりします。屈折異常の種類のよって見にくさは様々ですが、他に目の病気がない場合は、眼鏡やコンタクトレンズ等で視力を矯正します。
近視
角膜と水晶体の屈折率に対して眼球が長すぎる場合に起こります。光(映像)が網膜の前で焦点を結び、遠くのものが見えにくくなります。成長期に進行することが多いですが、大人でも進行することがあります。
遠視
角膜と水晶体の屈折率に対して眼球が短すぎる場合に起こります。光(映像)が網膜の後ろで焦点を結びます。小児や若年成人で軽度の遠視の場合は、水晶体の柔軟性に補われて網膜上に焦点を結ぶことができますが、加齢に伴い水晶体が硬化すると網膜上に焦点が結べなくなります。このため近くのもから見えにくくなり、程度によっては遠くのものも見えにくくなります。また、幼児期の高度遠視は弱視の原因となります。
乱視
角膜または水晶体にゆがみがあるため、距離に関わらずものがぶれて見えにくくなります。
老視
加齢で水晶体が硬化するために起こります。焦点を合わせる力が低下し、近くのものが見えにくくなります。元々の屈折の状態で見えにくくなる年齢は様々ですが、通常は40歳代の中頃を過ぎると症状が出現します。
弱視(3歳児健診で視力不良と診断される場合が多いです)
生まれたばかりの赤ちゃんはお母さんの影がぼんやりとわかる程度の視力しかありません。物を見る刺激によって徐々に視力は発達し、大人と同じくらいの視力になるのはおおむね6歳程度と言われています。視力が発達する時期に何らかの目の疾患があると成長が途中で止まってしまい、その後にどんなに眼鏡で矯正しても視力が出ない弱視になってしまいます。弱視の原因には強い遠視や乱視による屈折性弱視、左右の屈折が違うために片眼の視力が発達しない不同視弱視、斜視があるために生じる斜視弱視、その他先天性眼瞼下垂や先天白内障・先天緑内障等の疾患があります。視力の発達期である幼少期に眼鏡による屈折矯正や斜視・疾患の治療・弱視訓練などの治療を行い視力の発達を促すことが重要です。当院では医師・視能訓練士が診断・眼鏡処方・弱視訓練を行い、それ以上の治療が必要な場合は九州大学病院や福岡市立こども病院を紹介しています。

白内障
水晶体が混濁し視力が低下するものです。眼鏡等で矯正しても水晶体が混濁したことによるかすみや視力低下は改善しません。糖尿病・アトピー性皮膚炎・外傷・薬の副作用などが原因で起こることもありますが、ほとんどは加齢による水晶体の混濁が原因です。白内障の進行の程度は個人により様々で、視力低下などの自覚症状がない場合でも、60歳前後になればほとんどの方に白内障があります。混濁してしまった水晶体は目薬などでは治らず、あくまでも進行を遅らせる程度のものです。このため、日常生活に不自由を感じるようになれば手術治療が必要となります。当院では日帰りの白内障手術を行っています。視力低下や水晶体の混濁の程度は人によって様々ですのでよく相談の上、手術時期を決めています。

白内障1
水晶体皮質の混濁がおこり、かすみやまぶしさを感じたりします。

白内障2
混濁が進み視力が低下します。
白内障日帰り手術
当院では、年間300症例ほどの白内障日帰り手術を毎週水曜日の午後に行っています。手術は片眼ずつ行います。まず、手術日を決めて手術に必要な検査や説明などを行います。時期によって異なりますが、手術まで1~2か月程度の予約待ちがあります。
手術日は手術の1時間ほど前に来院していただき、目薬、血圧測定などの準備をします。手術時間は、白内障の程度や術式によって異なりますが、15分程度です。術後は眼帯をしてお帰りいただき、翌朝受診後に眼帯を外します。自宅ではできるだけ安静にしていただきます。基本的に翌日(木曜日)、翌々日(金曜日)と翌週の月曜日に受診が必要です。それ以降は医師の指示に従っていただきます。術翌日から日常生活は可能ですが、洗顔や洗髪は5日ほどできません。お仕事については、仕事内容によって異なりますのでご相談ください。
当院での手術が難しい症例や通院が難しい方、病気のため入院をご希望の方は、入院できる連携医療機関をご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。
緑内障
緑内障は視神経がダメージを受け徐々に視野が狭くなっていく病気です。日本の失明原因の第一位であり、40歳以上の約20人に一人が緑内障と言われています。
初期の緑内障は自覚症状に乏しく、気付かないうちに症状が進行してしまいます。片眼の視野が欠けても反対の眼が補うため視野が欠けていることに気づかず、自覚症状が出た時にはかなり進行し視力も低下していることが多いです。主な原因は目の中を循環している水(房水)の流れが妨げられ、眼圧が上昇して視神経がダメージを受けることですが、日本人には眼圧が高くないにもかかわらず起こる正常眼圧緑内障が多いといわれています。
治療は目薬で眼圧を下げることが基本です。一度欠けた視野は残念ながら元には戻りませんので、いかに早く緑内障を発見し、進行を遅らせるかが重要です。目薬の継続や定期的な眼科通院がとても大切になります。緑内障の目薬は多くの種類があります。視野進行の状態を見極めながらそれぞれの方にあった目薬を処方します。それでも視野が進行し緑内障の手術が必要な場合は連携医療機関をご紹介します。また、緑内障には急激に眼圧が上昇し、数日で視機能が損なわれる急性緑内障発作があります。この場合は目薬と点滴治療に加えてレーザーや手術など早急な対応が必要になります。急激な眼痛や吐き気、視力低下が生じた場合は眼科を受診してください。
網膜疾患
糖尿病網膜症
糖尿病は血糖値が高い状態が続くことにより全身の血管が損傷を受け様々な障害を引き起こす病気です。糖尿病網膜症は糖尿病腎症・神経症とともに3大合併症のひとつで我が国の中途失明原因の上位に位置します。高血糖により網膜の微小血管が障害を受け出血や閉塞が起こります。このため網膜の隅々まで血液が行き渡らずに網膜が酸欠状態となり、それを補うため新生血管が生じます。新生血管はとてももろいため容易に大きな出血を起こし、これを起点に硝子体出血や網膜剥離、緑内障など失明に至る疾患を引き起こします。また、物を見るのに重要な黄斑部(網膜の中心部)に傷んだ血管から血漿成分が漏れ出ると黄斑部がむくみ、黄斑浮腫という状態になり視力が低下します。
治療は内科的な糖尿病の血糖コントロールが最も大切ですが、進行した網膜症には新生血管の発症予防のため網膜に光凝固術を行います。これはレーザーによる治療で視力を回復するものではありませんが、網膜症の進行を予防し失明を防ぐためにはとても大切な治療です。硝子体出血や網膜剥離を発症した場合は手術が必要になりますので。手術のできる連携医療機関をご紹介します。また、黄斑浮腫で視力が低下した場合は、当院外来で血管からの漏れを抑制し網膜のむくみを減らすために抗VEGF薬を硝子体内に注射します。
網膜血管閉塞症
網膜の血管が詰まる病気です。網膜の血管には網膜に血液を送る動脈と血液を心臓に返す静脈とあります。
- 網膜動脈閉塞症
網膜の動脈が閉塞すると血液が途絶え、その領域の網膜の機能が失われ見えなくなります。迅速な対応が必要ですが回復が困難なことが多いです。 - 網膜静脈閉塞症
網膜の静脈が閉塞すると閉塞した血管の末端から行き場の失った血液が網膜に漏れ出し、出血やむくみが起こります。黄斑部に付近に起こると視力が低下します。糖尿病網膜症と同様に網膜に酸欠状態が起こると新生血管を生じ硝子体出血を引き起こすこともあります。治療は黄斑部の網膜のむくみや新生血管を抑えるために抗VEGF薬を硝子体内に注射します。また、網膜の酸欠が進行した部位には新生血管発生予防のために網膜光凝固を行うこともあります。
加齢黄斑変性症
治療は新生血管を抑えるために抗VEGV薬を硝子体内に注射します。黄斑部の網膜の障害が進むと視力が難しくなります。疫学的に喫煙が加齢黄斑変性症の発症と非常に高い相関があるといわれています。
抗VEGF薬の硝子体内注射
網膜剥離
ぶどう膜炎
アレルギー疾患